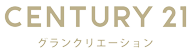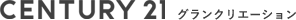離婚に伴う不動産売却の基礎知識 | 甲子園の不動産売却・買取・住宅購入はセンチュリー21グランクリエーション
離婚に伴う不動産売却の基礎知識

近年離婚による売却のご相談が増えております。特に共有していた自宅の不動産は、離婚協議の中でも最もトラブルになりやすいテーマのひとつ。この記事では、「離婚による不動産売却」をテーマに、基本的な仕組みから実際の手続き、税金・費用のポイント、トラブル回避策までをステップごとに解説します。初めての方でも安心して進められるよう、具体的な流れと注意点を網羅。スムーズな売却を実現し、新しい生活への第一歩を後押しします
基本前提
離婚時の不動産は、**誰の名義であっても、結婚後に取得したものは原則「共有財産」**とみなされます
=財産分与の対象
・婚姻後に購入した不動産 → 原則「共有財産」=財産分与の対象
・名義が夫単独でも関係なし
・妻が収入ゼロ・専業主婦でも、家事労働は「貢献」と評価され、2分の1の請求権あり
離婚と不動産売却の基本概要
1-1. 離婚時の不動産取り扱いパターン
離婚時に不動産を処分する方法は主に3パターンあります。
■売却して現金を分割:最もシンプル。市場に出し、売却代金を公平に分配。
•家を売って現金化 → たとえば売却益が1,000万円なら、それを500万円ずつ分ける
•ローンが残っていれば「売却価格 − ローン残高」が清算対象
•売却益が出るなら譲渡所得課税に注意(3,000万円特別控除が使える可能性)
→ 公正・シンプルだが、どちらも住み続けることはできない
■どちらか一方が買い取る:片方が共有持分を現金で買い取り、名義を一人にする方法。
たとえば妻が住み続けたい場合に選ばれる方法。
•評価額を査定(例:2,000万円)し、2分の1(1,000万円)を夫に支払う
•不動産の「所有権移転登記」が必要
•名義変更後の固定資産税、維持費、ローン返済も引き継ぐ
→ 住み続けたい・子育て環境維持したい場合などに有効
■共有名義のまま維持:売却せず、名義を共有して賃貸運用などを続けるケース。
1-2. 共有名義の仕組み
共有名義の不動産は、持分割合に応じた意思決定が必要です。
■共有物分割請求:裁判所を介して物件を売却・分配する手続き。協議がまとまらない場合の最終手段。
【ポイント】
離婚協議の段階で「売却」「買取」「維持」のいずれにするか大枠を決め、後の手続き負担を
軽減しましょう。
2. 売却を検討する前の準備と合意形成
2-1. 不動産の現状把握と査定
まずは物件の状態、ローン残債、固定資産税評価額を確認します。
■自宅の査定依頼:相場を把握し、適正価格設定の材料に。
■リフォームやハウスクリーニングの検討:少額の投資で売却価格アップを狙える場合も。
2-2. 公正証書・離婚協議書の作成
売却方法や代金分配比率を明確に文書化。
■公正証書にすることで、約束不履行時に強制執行が可能。
■離婚協議書には売却方針、期限、必要な各種手続きの担当者を記載。
【ポイント】後々のトラブル防止に正式な書面で合意を残しましょう。
3. 売却手続きの流れと必要書類
3-1. 仲介会社選びと媒介契約
信頼できる不動産会社を選ぶポイントは以下の通り。
■お住まいのエリアに特化した会社か
■査定価格の根拠説明が具体的か
■広告戦略(ネット・折込・ポータルサイト等)の幅
媒介契約は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類。手間や広告量とのバランスで選択します。
3-2. 売買契約と決済
購入希望者との価格交渉、重要事項説明の聴取後に売買契約を締結。
■手付金の授受:買主からの手付金が契約履行の証。
■決済(引渡し):司法書士立ち会いのもと、残代金受領と所有権移転登記を実施。
【ポイント】
契約書や重要事項説明を必ず自分でも目を通し、疑問点はその場で仲介会社に確認しましょう。
4. 注意すべき税金・費用と節税対策
4-1. 譲渡所得税の計算方法
売却益(譲渡所得)は「売却価格-(取得費+譲渡費用+特別控除)」で算出。
取得費とは購入時の価格やリフォーム費用、譲渡費用には仲介手数料などが含まれます。
4-2. 特例の適用可否
■買換え特例:一定要件を満たせば譲渡所得の繰延べが可能。
■居住用財産の3,000万円特別控除:居住用財産の3,000万円特別控除とは、自分が住んでいた家や土地を売ったときに、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。
•対象:自分が住んでいた住宅やその土地
•控除額:譲渡所得から最大3,000万円を控除
•条件:①自分が住んでいたこと(空き家でも一定条件で可)②親子・夫婦など特別な関係への売却でないこと
③譲渡から確定申告が必要
※さらに詳しく知りたい方は、国税庁のホームページで確認してみてください。
【ポイント】
売却時期や要件次第で数十万〜数百万円の節税になる可能性があります。
税金の話は、税務署や税理士に早めに相談を。
5. トラブル回避のためのアドバイス
5-1. コミュニケーションの取り方
感情的にならず、事実ベースで情報を共有。
- 定期的なミーティング日程を決める
- メールやLINEで記録を残す
5-2. 専門家への相談タイミング
- 離婚協議開始直後:弁護士・司法書士に大枠を相談
【ポイント】
専門家は“高いだけ”ではありません。早期相談が結果的にコスト削減と精神的負担軽減につながります。
まとめ
離婚による不動産売却は、感情的にも手続き的にも複雑ですが、適切なステップを踏むことでスムーズに進められます。
①売却のパターンを協議で明確化
②現状把握と書面での合意形成
③信頼できる仲介会社選びと契約内容の確認
④税務面の特例活用で最大限の節税
⑤専門家の適宜活用し、トラブル防止を未然に防ぐ
これらのポイントを押さえつつ、冷静かつ計画的に進めることで、新しいスタートへ向けた資金を確保し、
円滑な離婚手続きと生活再建を実現しましょう。
ページ作成日 2025-04-20
お客様主義でご対応いたします
ご売却について
ご売却・買取の
ご相談もお任せください。
お客様に合わせた
ご提案をいたします。